掲載日/2020年3月15日 取材・写真・文/やかん
取材協力/サイクルパーツ合同展示会、井上ゴム工業、パナレーサー、マルイ
予想外に好評でした 1 回目の実力派 26 インチタイヤ特集。あれから新たに取材ができましたので、追加のマウンテンバイク用 26 インチタイヤを紹介したいと思います。
今回は、ほとんどが日本ブランド & 国内生産なので、ある意味、国内の土質に合っているのではないでしょうか?
アイアールシー( IRC )
あとに上げるパナレーサーと合わせて、古くから日本のスポーツサイクル用タイヤの、特にレースタイヤの能力向上を牽引してきた片翼。最大の違いは、IRC はモーターサイクルのタイヤも多く手掛けていること。特にオフロード分野には強く、その意味でもマウンテンバイク用タイヤに寄せる期待と信頼は大きい。開発陣での、自転車とモーターサイクルの情報共有はあるようだ。
◇ミトス XC(MYTHOS XC)

まず、この時世に幅違いで 3 種類ラインナップしていることを称賛したい。古くからある、クロスカントリーレースに於ける定番タイヤで、サイズ展開はその名残とも言える。メーカー曰く、「XC レースで勝つ!」ことを至上タスクとして開発されたレース直系のモデル。
センターからショルダーのブロックを 2 段形状にして、剛性と耐摩耗性をキープしたままに小型・軽量化。それでいて、グリップ性能と耐パンク性能を疎かにはしていない。
昨今の高速系コースでは太めをチョイスしたくなるが、後輪のみ軽さを狙って細めを履く、というのもひとつ。ブロックパターンが各サイズごとの専用設計になっていて、それぞれのパフォーマンスを最大限に引き出せるよう配置を最適化しているとのことなので、レース用途では事前のテストをお勧めしたい。
サイズ/26 × 1.95
ETRTO/53 – 559
コンパウンド/表記はないが、従来から変更なし
重量/525g

サイズ/26 × 2.10
ETRTO/57 – 559
コンパウンド/表記はないが、従来から変更なし
重量/595g

サイズ/26 × 2.25
ETRTO/60 – 559
コンパウンド/表記はないが、従来から変更なし
重量/610g
価格/5,060円 / 共通(10%税込み)
すべて、折り畳み可能
◇ミブロ – X(MIBRO – X)

オールラウンド特性のマウンテンバイク用タイヤである『ミブロ』をベースに、さらにエキストリームな使い方(IRC では“アソビ”と表現)に対応させた、アドバンスドグレード。従来品であるミブロのパターンを徹底的にチューンナップし、ハードパックな路面でも音を上げない剛性を得た。グリップ性能にも優れる。
なお、2.40 サイズより 2.25 の方が重いのは、タイヤ内部の構造が違うため。2.25 サイズには、ビード部にゴムを入れてこの付近の強度を持たせたブレーカーが使われている。
サイズ/26 × 2.25
ETRTO/60 – 559
コンパウンド/表記はないが、従来から変更なし
重量/875g
サイズ/26 × 2.40
ETRTO/100 – 559
コンパウンド/表記はないが、従来から変更なし
重量/770g
価格/5,060円 / 共通(10%税込み)
どちらも、折り畳み可能
◇ブリロ(BRILLO)

マウンテンバイクのルックスやイメージを損なわない、ということで同社ではアーバン向けにカテゴライズされる街乗り用ブロックタイヤ。だが、筆者は 10 年以上使い続けていてダートでの性能になんら問題のないことを確認している。
ポイントは耐久性と価格だが、その分、重量はどうしても犠牲になっている。センターリッジのパターンになっていて、転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー & 強化してもいる。スチールビードなので、折り畳みはできない。

サイズ/26 × 1.75
ETRTO/47 – 559
コンパウンド/−
重量/790g
価格/オープン(実勢価格 3,000円 前後)
サイズ/26 × 2.00
ETRTO/54 – 559
コンパウンド/−
重量/900g
価格/オープン(実勢価格 3,000円 前後)
なお、ミブロ for マラソン チューブレスレディ(MIBRO for MARATHON TUBELESS READY) サイズ/26 ×2.25(19635E)は、廃番とのこと。残念!
パナレーサー( Panaracer )
先に紹介したアイアールシーと共に、国内レースシーン用タイヤの両翼を担う存在。26 インチタイヤの数は 1 モデルのみとなってしまったが、以前から決戦用チューブやコストパフォーマンスに優れたタイヤレバーなど、周辺アイテムの充実が目立つ。近年は、新タイプの空気入れを開発し(ワンタッチポンプ)、ラインナップを増やしてもいる。
◇マッハ SS(Mach SS)

高速系マウンテンバイク用タイヤの走りともなった、マッハシリーズ。『SS』は、その中でも最も低抵抗のセミスリックトレッドモデルとなる。見た目はグリップ力に劣るように感じるが、当時からよく考えられたパターンで問題はない。基本的にはハード & ドライコンディション用のタイヤなので、マディでの挙動は事前にテストしておくのが望ましい。
全体的に耐久性にも優れているため、ロングライフという面でも魅力が強い。コンパウンドは、特に名称はないが耐摩耗に優れた物を採用。ケーシングは、太いナイロンコードを使用した『800D Strong Cord(800D 強化コード)』。ビード部に、厚みのあるチェーファを採用し(ASB Chafer / アンチスネークバイト チェーファ)、耐リム打ちパンクに優れる。
ビード自体はスチールなので、折り畳みはできない。
サイズ/26 × 1.95
ETRTO/53 – 559
コンパウンド/−
重量/650g
価格/3,279円(10%税込み)
タイオガ(TIOGA)
かつては、国産で良質なタイヤを多く出していた三ツ星に委託したレース用マウンテンバイクモデルをラインナップ。現在は、三ツ星のタイヤ事業廃業により、かなり後退。その中でも、今回紹介する 1 モデルだけは台湾で他社のレースタイヤと同じ製造ラインで作られる。
◇サイコ II(Psycho – II)

過去に存在したタイオガの名作『サイコ』の、普及モデル。路面コンディションを選ばないオールラウンド仕様で、価格を含め入門用にも最適なタイヤ。折り畳み不可。
サイズ/26 × 1.95
ETRTO/52 – 559
コンパウンド/AP ラバー コンパウンド
重量/710g
価格/3,080円(10%税込み)
今回紹介するマウンテンバイク用タイヤは、これで以上になります。ほとんど過去からの継続モデルなので“チューブレスレディ”には非対応ですが、新品ゴムで 26 インチタイヤが入手できるのは助かるところであります。
ちなみに、ある問屋の話しでは 26 インチのマウンテンバイク用タイヤは、アメリカに於いては日本比で 5 倍くらいの需要があると言います。車体自体の買い替え意欲がないのか、物を大事に使う文化なのか、判断は難しいところですが「持続可能」という言葉ばかりが踊る昨今、ひとつ、見つめ直すべき点ではないでしょうか?
関連:1 回目の特集
【マウンテンバイク】2020年にまだ26インチのマウンテンバイクは闘えるのか?(MTBタイヤカタログ) ※情報追記

ダート&モト編集部
サトウハルミチ(やかん) Harumichi Sato
東京都生まれ千葉県育ちで、身長 156cm の mini ライダー。紙媒体の編集を長く経験した後、2012 年 4 月から初めて WEB マガジンに携わる。戦車から爆撃機まで無類の乗り物好きで、特に土の上を走る四輪・二輪に目がない。競争事も好きで、マウンテンバイク / モトクロスはレース経験あり。モーターサイクル / スポーツサイクル以外にフィルムカメラ、ホームオーディオ、クルマ、紙の読書(恩田 陸先生の大ファン)、ガンプラが大好きで、住まいはモノで溢れている。特技は、引き落としの滞納。スポーツサイクルは、マウンテンバイク 6 台と BMX 1 台を所有。
- 当サイトに含まれるすべてのコンテンツ(記事・画像・動画・イラストなど)の無断転用は、商用、個人使用を問わず一切禁じます。
© yakan_Dirt & MOTO All rights reserved.

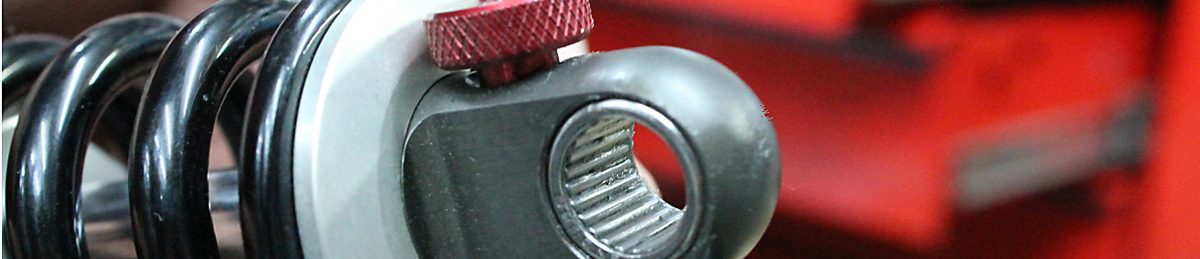

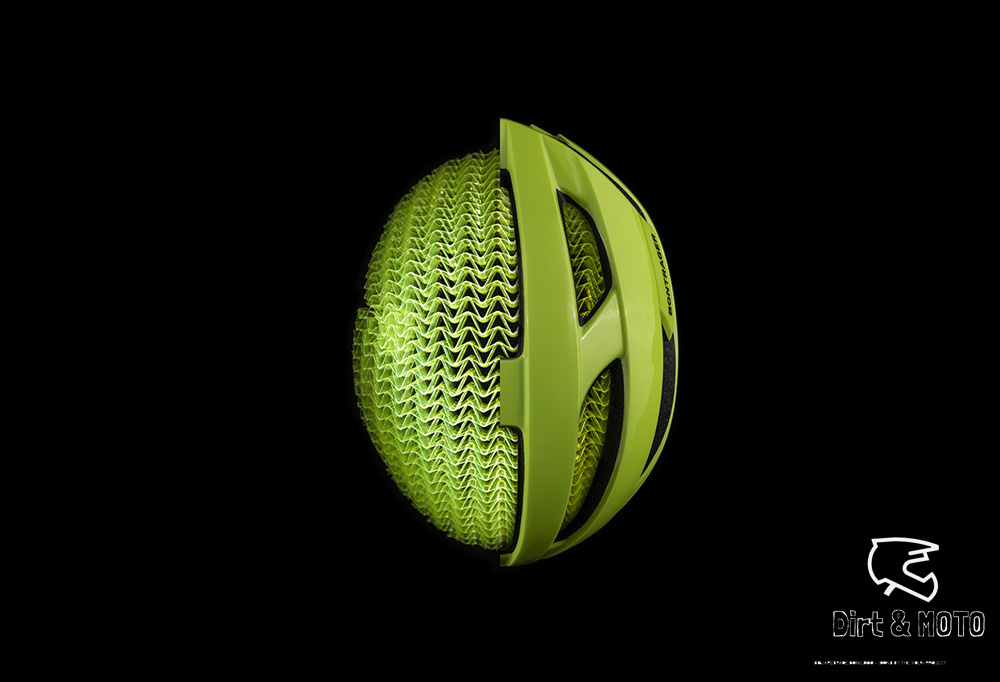















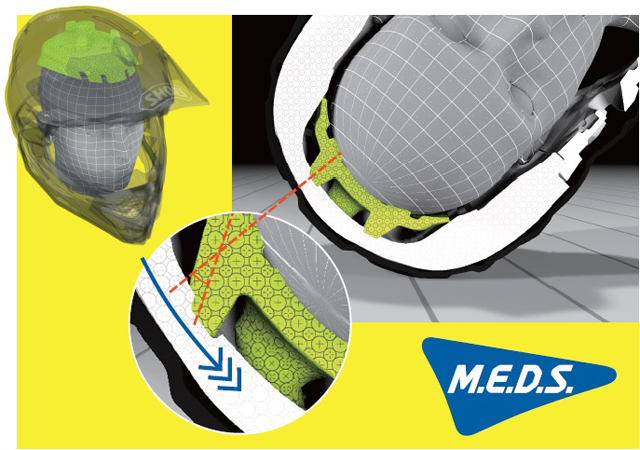




















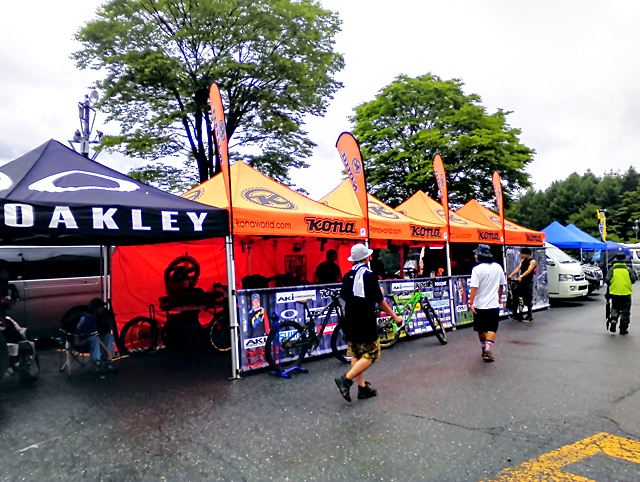












 フロントサスペンションは、DT Swiss XRC100 Race Remote。特徴的なアーチは『HOLLOW ARCH』と呼称され、ロワーまで含めカーボン製となる。軽量さが売りで単体、1,250g。トラベル量は100mm。
フロントサスペンションは、DT Swiss XRC100 Race Remote。特徴的なアーチは『HOLLOW ARCH』と呼称され、ロワーまで含めカーボン製となる。軽量さが売りで単体、1,250g。トラベル量は100mm。 サスペンションは右側手元でのロックアウトが可能。O.NINE PRO TEAM ISSUE同様、SRAMのシフター(XX)はインジケーターがないタイプで、プロ選手には不要の物なのだろうか? ギアレシオは2×10なので、特にフロントギアには必要ないのかもしれない。
サスペンションは右側手元でのロックアウトが可能。O.NINE PRO TEAM ISSUE同様、SRAMのシフター(XX)はインジケーターがないタイプで、プロ選手には不要の物なのだろうか? ギアレシオは2×10なので、特にフロントギアには必要ないのかもしれない。 性能や仕様の違いの表記はないが、SUPERLITE TEAMは“ウルトラ”ハイモジュラスカーボンファーイバーをフレームに使い、やはりこの2013年モデルからシートステーにバイオファイバーが加えられた。メリダのこのカーボンバックは本当に秀逸。
性能や仕様の違いの表記はないが、SUPERLITE TEAMは“ウルトラ”ハイモジュラスカーボンファーイバーをフレームに使い、やはりこの2013年モデルからシートステーにバイオファイバーが加えられた。メリダのこのカーボンバックは本当に秀逸。 曲げや捻れ剛性を向上しつつ、衝撃への耐久性を上げ軽量化にも寄与するというDouble Chamber Technologyも使われる。ボトムブラケット規格はBB30を採用し、ダイレクトでロスの少ないペダリングを実現する。
曲げや捻れ剛性を向上しつつ、衝撃への耐久性を上げ軽量化にも寄与するというDouble Chamber Technologyも使われる。ボトムブラケット規格はBB30を採用し、ダイレクトでロスの少ないペダリングを実現する。 ブレーキは油圧式SRAM XX。ローターにはセンターロックの、同じくSRAM XXを使い、前がφ180mm、後がφ160mmの異径組み合わせ。フローティングにも見える、ややスーパースポーツな外観。
ブレーキは油圧式SRAM XX。ローターにはセンターロックの、同じくSRAM XXを使い、前がφ180mm、後がφ160mmの異径組み合わせ。フローティングにも見える、ややスーパースポーツな外観。 コンポーネンツ系はすべてSRAM XXで統一し、フロントチェーンリングはグループ会社のトゥルバティブの2枚タイプになる。42-28Tと歯数が極端に離れ、またクランク長は175mmと標準の日本人には長過ぎるかも。
コンポーネンツ系はすべてSRAM XXで統一し、フロントチェーンリングはグループ会社のトゥルバティブの2枚タイプになる。42-28Tと歯数が極端に離れ、またクランク長は175mmと標準の日本人には長過ぎるかも。

 フロントサスペンションは、DT Swiss XRM 100 Remote。特徴的なアーチはTORSION BOXと呼称され、ローワーと一体成形されるマグネシウム製。内部構造はエア式で、Auto Balancing Springを採用。トラベル量は100mm。
フロントサスペンションは、DT Swiss XRM 100 Remote。特徴的なアーチはTORSION BOXと呼称され、ローワーと一体成形されるマグネシウム製。内部構造はエア式で、Auto Balancing Springを採用。トラベル量は100mm。 サスペンションは右側手元でのロックアウトが可能。シフターはSRAMのX9で、インジケーターがないタイプ。個人的には不便に感じる。ギアレシオはベーシックな3×10になる。メリダの純正グリップはスポンジ状が多く、なかなか具合が良い。
サスペンションは右側手元でのロックアウトが可能。シフターはSRAMのX9で、インジケーターがないタイプ。個人的には不便に感じる。ギアレシオはベーシックな3×10になる。メリダの純正グリップはスポンジ状が多く、なかなか具合が良い。 ハイモジュラスカーボンファーイバーをフレームに使い、2013年からはシートステーにバイオファイバーが加えられた。メリダはガーボン成形のレベルも非常に高く、Nano Matrix Carbon、Anti Wrinkle Systemなど独自の技術を多く持つ(本機も採用)。
ハイモジュラスカーボンファーイバーをフレームに使い、2013年からはシートステーにバイオファイバーが加えられた。メリダはガーボン成形のレベルも非常に高く、Nano Matrix Carbon、Anti Wrinkle Systemなど独自の技術を多く持つ(本機も採用)。 カーボンチューブ内にリブを入れたメリダ独自の技術、Double Chamber Technologyを採用する。2つの独立したチャンバー(空洞)をフレーム内に設ける事で、曲げや捻じれに対する剛性を大幅に上げ、衝撃に対する耐久性も向上させている。
カーボンチューブ内にリブを入れたメリダ独自の技術、Double Chamber Technologyを採用する。2つの独立したチャンバー(空洞)をフレーム内に設ける事で、曲げや捻じれに対する剛性を大幅に上げ、衝撃に対する耐久性も向上させている。 ブレーキは前後に油圧式ディスクのMagura MT4を採用。昨今のクロスカントリーは平均スピードの上昇と下りセクションの激化が進んでいるため、対応してローター系は前がφ180mm、後ろがφ160mmになる。デザインも最新の物に。
ブレーキは前後に油圧式ディスクのMagura MT4を採用。昨今のクロスカントリーは平均スピードの上昇と下りセクションの激化が進んでいるため、対応してローター系は前がφ180mm、後ろがφ160mmになる。デザインも最新の物に。 O.NINEもトップチューブにアイコン的グラフィックが入れられる。ヘッドチューブは同社オリジナルの、中心部が膨らんだEgg-Shape形状。セミインテグラルのヘッドパーツと組み合わせる事で、剛性を高めている。塗装の仕上がりも素晴らしい。
O.NINEもトップチューブにアイコン的グラフィックが入れられる。ヘッドチューブは同社オリジナルの、中心部が膨らんだEgg-Shape形状。セミインテグラルのヘッドパーツと組み合わせる事で、剛性を高めている。塗装の仕上がりも素晴らしい。

 フロントサスペンションは、DT Swiss XRM 100 Remote。エアスプリングでAuto Balancing Springという機構を持つ。黒いインナーチューブとリバースアーチが特徴的。
フロントサスペンションは、DT Swiss XRM 100 Remote。エアスプリングでAuto Balancing Springという機構を持つ。黒いインナーチューブとリバースアーチが特徴的。 リアサスペンションにはM.O.R.E(Merida Optimized Ride Engineering)と呼ぶリンクが使われる。ユニットはDT SwissのM212 38 ABS w/Remote。
リアサスペンションにはM.O.R.E(Merida Optimized Ride Engineering)と呼ぶリンクが使われる。ユニットはDT SwissのM212 38 ABS w/Remote。 油圧ディスクブレーキは前後に名門Magura MT4を採用。長くハードな下りも含まれるマラソンステージを想定してか、ローター径はフロントが180mm、リアは160mm。
油圧ディスクブレーキは前後に名門Magura MT4を採用。長くハードな下りも含まれるマラソンステージを想定してか、ローター径はフロントが180mm、リアは160mm。 ハンドル右側にフロントサスペンション用のロックアウトリモートを装備。シフターはスラム X9。
ハンドル右側にフロントサスペンション用のロックアウトリモートを装備。シフターはスラム X9。  リアユニット用もロックアウト出来るため、ハンドル左側にリモートを装備。前後ともロックアウト出来ると左右に異なるリモートが備わり、操作は複雑になる。
リアユニット用もロックアウト出来るため、ハンドル左側にリモートを装備。前後ともロックアウト出来ると左右に異なるリモートが備わり、操作は複雑になる。 フロントギアは2枚の、2×10ドライブトレインを採用。チェーンリングとクランクは、スラムのグループ会社になるトゥルバティブ製。丁数は38-24T。
フロントギアは2枚の、2×10ドライブトレインを採用。チェーンリングとクランクは、スラムのグループ会社になるトゥルバティブ製。丁数は38-24T。